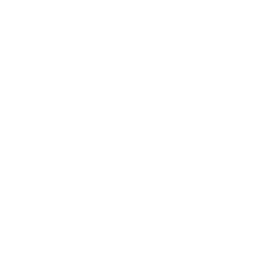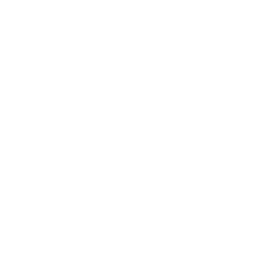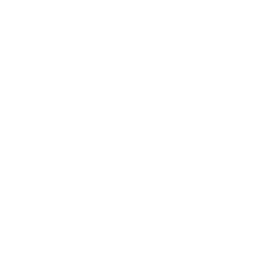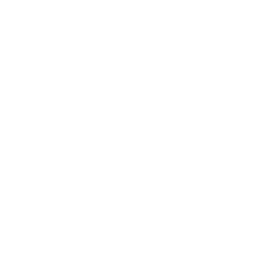秋が旬!眼精疲労に効く!菊花の知られざる効能
こんにちは!ブランドクリエイターのMAG-CHANです。
今回は、少し前に「フラワーレーベル」に追加した新フレーバー「菊花と紫蘇」に使用している、
「菊花」をフィーチャーしたいと思います!
ちょうど秋に旬を迎えるのでタイムリーなお花です。菊の花と聞くと、お盆やお彼岸、
仏前にお供えする花とかのイメージが強いかと思います。
私もそのように考えていました!なんなら縁起が悪いかもとまで悲観的なイメージでした。。
ところが、実は私たちの日常に寄り添ってくれる効能がたくさんあることがわかりました!
そして案外身近な存在だということも。。。
知ればご自愛タイムに活用したくなること間違いなし。ぜひご参照ください!
【菊花の特徴】
分類:キク科キク属
利用部位:花(乾燥させて薬用茶や漢方薬に)、花弁(食用菊として料理に)
→秋を代表する花で、日本・中国で古来より観賞用・薬用・食用に利用される。花の色は白、黄色、紫など多様である。食用菊では、「延命楽(えんめいらく)」や「阿房宮(あぼうきゅう)」などの品種が有名。薬用菊花は乾燥して「菊花茶」として利用される。
菊は用途によって使われる品種も様々となっている。
~観賞用菊(園芸菊)~
日本では特に品種改良が盛んで、数千種類以上ある。主に「花の大きさや形」で分類される。
*大菊(おおぎく):直径20cm以上。展覧会用に育てられる(例:厚物菊、管物菊、広物菊)。
*中菊(ちゅうぎく):直径10〜20cm。切り花や仏花として流通。
*小菊(こぎく):直径10cm未満。鉢植えや庭園用に人気。
*洋菊(スプレーマム):西洋で品種改良された小花タイプ。フラワーアレンジに使われる。
*江戸菊・嵯峨菊・伊勢菊:日本独自に発展した古典菊で、細い花弁や優雅な姿が特徴。

~食用菊(食べられる菊)~
食用専用に改良された苦味の少ない品種。特に東北地方(山形・新潟)が有名。
*延命楽(えんめいらく):山形県原産。紫紅色でシャキシャキした食感。酢の物やおひたしに。
*阿房宮(あぼうきゅう):黄色い大輪。新潟県特産。香りがよく、天ぷらや和え物に。
*もってのほか:山形の有名品種。名前の由来は「天皇の御紋の菊を食べるなんてもってのほか」。
シャキッとした食感が特徴。
※春菊はキク科シュンギク属の葉野菜で厳密には菊花とは異なるが食用菊の仲間である。

~薬用菊(漢方・菊花茶用)~
中国で伝統的に薬効を重視して育てられてきた品種。乾燥して「菊花茶」や漢方薬に使われる。
苦味があり、清熱・解毒作用が高いとされる。体を冷ますお茶として利用。
*杭菊(こうぎく)(浙江省杭州市原産)…菊花茶の代表品種。淡い黄色、小ぶりで上品な香り。
*胎菊(たいぎく)…つぼみの状態で収穫。香りが濃く、甘みが強い。高級品として珍重。
→「菊花と紫蘇」では高品質な『胎菊』を使用しています♪
*甘菊花…甘みのある香りで飲みやすい。リラックス効果が強い。
*苦菊花…苦味があり、清熱・解毒作用が高いとされる。体を冷ますお茶として利用。

観賞用の菊は日本独自に改良がなされ、独自の文化になっていると言っても過言ではなさそうですね。
昔から観て楽しむ花として親しまれていることがわかります。
また、食用としての菊は春菊も含めると案外身近です。お刺身に乗っているタンポポに似た黄色い花は
「阿房宮(あぼうきゅう)」という品種であることが多く、飾りだけでなく実際に花びらを使って食べることを想定して盛り付けられています。
~番外編「お刺身の菊の食べ方」♪
*花びらを散らす…花びらを一枚ずつ外して、刺身の上や醤油に浮かべる。香りと彩りを楽しめる。
*醤油に混ぜる…花びらを少量ちぎって醤油に入れると、ほんのり苦味と香りが移る。
脂ののった魚(ブリ・トロなど)と好相性。
*刺身と一緒に食べる…白身魚(鯛・ヒラメなど)に少量の花びらをのせて食べると、
さっぱりした風味が加わる。
*残りを小鉢料理に…余った花びらを酢の物や和え物に加えても美味しい。
⇒こんな通な楽しみ方があったとは驚きですね!さっそくお刺身を買いに行きたくなりました(笑)
【菊花の歴史】
~古代中国(紀元前〜漢代)~
原産地は中国北部~華北平原。紀元前15世紀ごろの甲骨文字や文献に、菊らしき植物の記録が登場。『神農本草経』(紀元1〜2世紀頃)にも薬草として記載があり、「服すれば久しくして身を軽くし、年を延ぶ」と記され延命長寿の薬とされた。中国では「延年益寿の花」として尊ばれ、解熱・解毒・目の不調に効く薬用植物として利用された。
~中国・魏晋南北朝~隋唐時代(3~9世紀)~
陶淵明の詩に「菊を愛でる心」が描かれ、清廉(心が清らかで欲がないこと)の象徴になった。
また、「重陽の節句(9月9日)」に菊の花酒(菊花を浸した酒)を飲み長寿祈願する風習が生まれた。
唐代には宮廷で菊を栽培する文化が広まり、観賞用の品種改良が始まった。
~日本への伝来(奈良時代〜平安時代)~
奈良時代(8世紀初頭)、中国から薬草や観賞植物として伝わる。平安時代(9世紀以降)、
宮中行事「重陽の節句」に取り入れられ、貴族の間で菊を鑑賞する文化が定着した。
「古今和歌集」などの和歌にも菊が登場し、秋を象徴する花として親しまれる。
~鎌倉~室町時代~
鎌倉時代(13世紀)には「菊紋」が「天皇家の紋章(十六八重表菊)として定着し、以後皇室の象徴と
なり現在もパスポートや公用印に用いられている。室町時代には観賞用として栽培が広がり、茶道や華道の花材にも用いられた。
~江戸時代(17~19世紀)~
菊の品種改良が盛んとなり、江戸(江戸菊)・京都(嵯峨菊)・伊勢(伊勢菊)など各地で「古典菊」が発展した。また、食用菊の栽培も東北地方(山形・新潟など)で始まり、酢の物・天ぷら・和え物として
庶民の食卓に広まった。
~近代~現代~
中国では現在も「菊花茶」が日常的に飲まれ、薬膳・養生文化の一部となっている。
日本では「皇室の花」としての象徴性と「秋を代表する花」としての鑑賞性を併せ持つ花として親しまれている。東北地方では食用菊文化が継続し、「もってのほか」「阿房宮「延命楽」などの品種が名産品となった。世界的にもガーデニングやフラワーアレンジメントで愛され、国花としての地位を確立していった。
【菊花の成分と効能】
菊花は観賞だけでなく、健康効果でも古来から重宝されてきました。中国の漢方や日本の民間療法では特に「目・頭・熱」に効くとされます。
~目の健康~
*成分…ルテオリン、アピゲニン(フラボノイド系)
抗酸化・抗炎症作用があり、目の充血・かすみ目・ドライアイを改善する。
漢方の「菊花茶」「杞菊地黄丸」などとして視力回復や眼精疲労に処方される。
~頭痛・めまい・のぼせの緩和~
*成分…ボルネオール、カンファー(精油成分)
鎮静・清涼作用により、頭部の熱感や緊張性頭痛を和らげる。
漢方では、体内の余分な熱や上昇した気を鎮める「清熱・平肝」という効能で扱われる。
~風邪予防・解熱~
*成分…クロロゲン酸、フラボノイド、ビタミンC
抗菌・抗ウイルス作用により風邪の初期症状に効果的。発熱やのどの痛みを抑え、体を涼しくする作用から、夏の暑気あたり(夏バテ・熱中症)にも用いられる。
~抗酸化作用・アンチエイジング~
*成分…ルテオリン、アピゲニン、クロロゲン酸
活性酵素を除去して細胞の老化防止・美肌効果・生活習慣病予防に役立つ。
~血圧調整・循環改善~
*成分…カリウム、フラボノイド類
血管を拡張し、血流を改善する。高血圧や動脈硬化の予防に期待される。
~リラックス・安眠~
*成分…カンファー・ボルネオール(精油成分)、フラボノイド
神経の緊張を和らげ、リフレッシュ効果と安眠をサポート。
菊花茶やアロマとして取り入れられることも多い。
【菊花×SPICE珈琲】
SPICE珈琲【Flower Label】の「菊花と紫蘇」は、厳選した中深煎りのコーヒー豆に紫蘇の葉と薬用菊の中でも高品質な「胎菊」をブレンドした、今までない和風テイストのフレーバーコーヒーです。紫蘇にも美肌効果や抗酸化作用のある成分が含まれ、アンチエイジングにうってつけのフレーバーです。
菊花の特性である眼精疲労を回復する効果も見逃せません。デスクワークの多い方には特におすすめです。スマホももはや必需品ですし、現代社会において眼精疲労は国民の問題となりつつある昨今、、今後需要が高まるかもしれませんね!!ぜひリンクからおためしください。
「ご自愛タイム」にお役立て頂けましたら幸いです。

SPICE珈琲のブランドビジョンは
「飲む人の心と身体に寄り添い、自分を大切にする時間をつくっていただく」ことです。
「SPICE珈琲」では、ご自分の状況に合わせたフレーバーをお選びいただけるよう、様々な場面を想像してブレンドをしています。
リラックス、気分転換、デスクワークのお供…etc.などテーマに沿ったフレーバーを展開しています。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
疲れたらほっと一息、入れてくださいね。
日常の息抜きタイムに「ご自愛カフェタイム:)SPICE珈琲」お役立て出来ましたら幸いです。